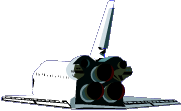在ヒューストン日本国総領事 加茂佳彦

テキサス6都市から本日マッカレンにご参集頂いた日本人ビジネスマンの皆様に講話をするという大役を仰せつかりました在ヒューストン日本国総領事の加茂佳彦でございます。当地のベテランでいらっしゃる皆様方に何をお話するのがよいのかテーマ選びに苦労いたしました。お手元に用意いたしましたレジュメをご覧になって頂ければお分かりのように、本日は、テキサス雑感と題しまして、私が当地での日頃の活動を通じても何かと考えさせられることが多い歴史問題と日本人のアイデンティティーにつきお話してみたいと思います。なーんだ、そんな話かと思われる方もいらっしゃるでしょうが、皆様のアメリカ生活にまったく無縁であるとは言い切れない問題ではないかと思います。歴史問題ですが、私はこの方面の専門家でもありませんし、これからお話する私見も、日本の総合雑誌に載っていたオピニオン・リーダー数人の論文を下敷きにして、自分なりに咀嚼したものに依っています。ただ、正直に話してみようと思います。
Ⅰ.歴史問題
過去1年在ヒューストン総領事として在勤いたしましたが、こちらで暮らしてみて初めて分かったことがいくつかございます。その一つが、日米戦争の負の遺産がなかなか消え去らないことです。昨年秋、ヒューストンのエリントン基地で航空ショーが開催されました。そこでは日本軍のパールハーバー攻撃が再演され、最大の呼び物になっていました。多分米国各地の航空ショーで、パールハーバー絵巻が毎年再現されているのでしょう。今年2月にフレデリクスバーグのニミッツ提督博物館でイラン・コントラ事件のノース中佐が硫黄島の戦いについての講演会を行っていました。5月のヒューストンでのミリタリー・ボールでも硫黄島ベテランが主賓として紹介され、盛んな拍手を受けていました。8月に私は原爆投下についての地元ラジオ局インタビューを受けました。揚げ足取りをされないように注意して応答しましたが、インタビュアーは、収録後、個人的には原爆投下は間違っていたと考えるとの心情を吐露してくれました。8月7日のヒューストン・クロニクルのトップ記事は、ヒューストン在住の被爆者の話でした。原爆投下は戦争を早期に終結させるため必要であったと考える米国人が大多数ですが、彼らとてもやはり気になると見え、毎年、やはり正しかったのだと再確認することが習い性になっているのかも知れません。
日米関係は最高と言われる昨今でもこの有様です。ことしが戦後60周年の節目だったこともあるのでしょうが、年中行事化していると言えそうです。21世紀になっても日本人、日系人は米国において年最低3回は歴史問題に晒される。これが、米での現実ではないでしょうか。歴史問題というと中国、韓国との歴史認識ギャップが頭に浮かびますが、日本の総領事としては、この米との間の歴史問題にも無関心ではいられません。
さて本年4月の中国での反日デモは米国でも広く報道されました。今回の一連の報道を通じて日中歴史問題への複眼的アプローチが実現しました。初めて日本の言い分にも注意が払われ、また、中国の姿勢を問題視する声も聞かれました。他方、米ジャーナリズムが日本の立場に深い理解を示すようになったということではありませんでした。中国の道義的優越に疑問符を打つ声が聞かれましたが、「どっちもどっち」との見解止まりでした。
4月の中国での反日デモの副次効果は、日本側(日本政府・在外公館)が率先して反論をするようになったことでしょう。海外論調のモニターと反論が在外公館の重要な広報事業になりました。但し、米国は民の国です。世論が政策を決定します。米国では民間からの発信が好まれ、信頼もされます。
歴史認識を巡る日中論争は、本年4月の反日デモの機に全世界的規模で燃え上がりました。靖国、教科書、謝罪、賠償等での応酬があり、一進一退でした。留意すべきは、平均的米国人から見ると日本の分が決して良くないことです。彼らにとって日本は、どう弁解しようと、侵略戦争を実施した加害者であります。そして被害者である中国や韓国が未だに怒っているのは、日本の反省が足りないからであろうと思っているのです。これら平均的米国人に対する日本の弁明の拠り所は、言論の自由と戦後60年の歩み(平和主義)にあると思います。靖国にせよ教科書にせよ、言論の自由、表現の自由の問題に帰着させることができるように思われます。日本の真意や実績へのアピールと共に日本は基本的人権が保障された民主主義国であり独裁政権国とは違うとの立論が最も理解を得られやすい論理であろうかと思います。
中国の反日姿勢の目的は何なのでしょう。多くの論者が指摘するのは、日本の道義性の欠如を指摘し、日本との関係で優位を確保するためです。中国としては中国中心のアジア秩序形成を目指す上で、優位を上手く活かしたいと思うのは当然でしょう。次に内政上のカードとしても重要です。中国は共産党独裁体制の正統性を抗日戦争に求めています。現在でも愛国心(反日)と経済発展が国民に求心力を与え、従って、政府に正統性を与えています。急激な市場経済化の矛盾や不満の捌け口として反日感情を利用している側面もありそうです。民衆の怒りはどうでしょう。誰でも成功した隣人は疎ましい者ですし、ましてや、してやられた日本に対しては憎悪が自然に湧いてくるものなのかも知れません。ただ、多くの論者が、教育による憎悪の増幅が与っていることを指摘しています。日中戦争を知っている世代よりも最近の若者の方が強い嫌悪感を抱いているとも言われております。政府の意向を忖度するような反日の空気が流れているのかも知れません。いずれにせよ、反日は、観念的に言えば、中国の損得均衡表から見て逆効果だと判断するまで続くでしょう。中国共産党の正統性や中国中心のアジア秩序形成がかかっているとしたら、反日がおいそれとなくなるわけがありません。当分続くものと覚悟せざるを得ないでしょう。
全く、なかなかやっかいな隣人ですが、日中論争の観察を通じて、先方の「作戦」が透けて見えて来るように思います。私見では、日中論争の構造を理解する上で次の視点が有益であると思います。第一は「被害者イメージの積極宣伝」が反日宣伝工作の基本だということです。面子を重んじる中国でありますが、対日情報作戦では、誇り高き鷹揚な中国人を繕わず、「哀れな中国人」のイメージ作りに腐心しているように見受けられます。中国は戦中時から外国の同情を買う情報操作を巧みに実施してきました。日本は国内の戦意高揚のため逆方向の情報操作を実施しました。このディスインフォメーションの構造が事実関係を歪めました。さらに日本の敗戦により、この歪みを是正することができない状況が続いています。第二は、「日独同罪」や「戦後処理はドイツを見習え」式のイメージ工作の実施です。ホロコーストと南京事件をリンクさせたい。ニュールンベルグ裁判と極東裁判を同一視させたい。日独同罪化は、歪曲された事実の定着に寄与するのです。
日本の立場にも理解を示す声が聞かれるようになってきたとは言え、欧米を中心に「日本人一般に見られる戦争責任をはっきりと認めたがらない態度」が問題だとする指摘があります。確かにそうかも知れません。日本人は、贖罪意識に囚われながらも、敗者として精一杯の消極的抵抗をしているのではないか。潔くない。ドイツを見習え。本当にそうでしょうか。翻って、歴史認識問題になると日本が感じる鬱々とした不満の種は何なのでしょう。不満の源泉はどこにあるのでしょう。
その第一は、不公平感でしょう。日本の罪、悪さを相対化して欲しいと言い換えてもよいかも知れません。20世紀前半の帝国主義日本の行跡が特に良かったとは申しませんが、特別に悪かったのか。ドイツとよく比較されますが、そもそも有効な比較が可能なのか。敗者同士の比較というなら、イタリアはどうなのか。理想主義からの糾弾も不公平な感じがします。21世紀的人道主義や人権思想を持ち出して、現代に至っても十分に遵守されないような行動規範を60年、70年前の日本軍に求めるのは酷ではないか。植民地支配が非難されるのならば、列強との比較で取り上げて欲しい。戦争犯罪で非難するのならば、敗者の戦争犯罪だけを非難するのでなく、勝者のそれも取り上げて欲しい。こう思うのです。
第二の不満は東京裁判が何となく腑に落ちないことでしょう。同裁判は、世界侵略の意図と共同謀議の実施という仮説に依拠して満州事変前後からの日本の動きに網を掛け、その戦争責任を糾弾しました。ところで日本政府は「サンフランシスコ条約で東京裁判を受け入れている」と明言しております。同条約では東京裁判の判決(judgement)を受け入れるとしていますが、単に、戦犯を刑死させることを認めたに過ぎないのか、この判決の基礎となる歴史認識、解釈を受け入れることまでを請け負ったと解釈するかで識者の間で議論があります。日本の知識人は、右派、左派ともに、この史観が真実の歴史を伝えていると思っている人は少ないようです。各種の不備が指摘され、また日本にとって厳しい内容の判決が言渡された東京裁判ですが、人道に対する罪は認定しませんでした。人道に対する罪を認定されたドイツの戦犯と日本の戦犯の違いはここにもあります。靖国問題において中韓がA級戦犯を殊更問題にするのは何故なのでしょうか。韓国は当時日本の一部であり、韓国出身の日本人も靖国神社に祭られています。植民地支配関係者はA級戦犯ではなく、靖国神社にはいません。また、中国関連でも、例えば日中戦争に最も深く関与したと言える満州事変の首謀者の石原莞爾はA級戦犯として起訴されませんでした。石井731部隊長も然りです。中韓はA級戦犯が日本軍国主義の象徴だと主張しますが、その多くは対米戦争関係者です。彼らが、日中戦争指導者、韓国植民地化政策指導者ではなく、A級戦犯に焦点を当てている狙いは何なのでしょう。これは要するに、A級戦犯を強調することにより、米国が世界に示した米国流の正義を利用しようとしているのではないでしょうか。そこには米国が作った土俵の上で日本に攻勢を仕掛けるのが最も安全で効果的であるとの判断があるように思われます。東京裁判と連動している限り、世界の通説として流布している東京裁判史観が中韓の主張を後押ししてくれますし、米も反論できないのです。
これは必ずしも日本が感じる不満ではありませんが、第三の視点として「戦争とはそういうものだ」という諦観に近い認識を指摘したいと思います。敗者の論理かも知れませんが、この認識が日本人の心情をよく表すのではないかと思います。
敗戦により敗者の立場を強いられます。日本は敗者の美学を実践してきました。時に応じて卑屈に振舞い、現秩序に挑戦せず、信頼の回復に努めました。敗戦国としての法律的、道義的責任も果たして参りました。他方、戦後60年が経ち、極東を巡る地政学的状況も一変し、この姿勢に少しずつ変化の兆しが現れてきました。日本の実績を認めようとしない中韓の態度に苛立ちを覚える人が増えてきたのです。
日本人も戦争遂行に伴い、甚大な戦争被害に遭いました。原爆や東京大空襲が先ず思い浮かびますし、戦後のシベリア抑留も痛恨時でした。しかしながら、日本人は敗者としての立場を弁え、自らの戦争被害を言い立てることは避けてきました。帝国主義時代を律したのは弱肉強食ルールです。負けるほうが悪いというルールです。言いたい事は色々ありますが、負けたからといって後から勝者に文句を言うのでは日本人の矜持が地に落ちてしまいます。「戦争とはそういうものだ」と言う忍耐を敗者の日本が示してきたのに、中韓は戦後60年も経っても「犠牲者スタント」を続けている。この中韓のポスチャーリングこそ、著しく世界の相場感を欠く態度なのではないか。そのことに世界は気付いて欲しい。日本としては、なかなか正面切って言えないクレームですが、平均的日本人の心の叫びでもあるでしょう。
これまで婉曲に触れてきましたが、我々は、東京裁判史観に基づく米国の歴史認識こそ、中韓の歴史認識の支えになっていることと向き合わなければなりません。日本が中韓の主張に本格的な反論をしようとすると、戦時中の米の戦争宣伝や東京裁判、占領中の検閲や思想統制、日米の戦後歴史教育等により定着した近現代史の通説に挑戦しなければならなくなってくるのです。米国人が日中論争を判断する際の基準も、この歴史観です。それが世界の通説であり史実であるとされており、異なる意見は、多くの場合、修正主義的意見として切り捨てられてしまいます。
歴史の解釈は、視点が変わればニュアンスが変わってくるものです。パールハーバーは、「卑怯な不意打ち」のイメージが今日まで増幅され、再生産されてきていますが、この攻撃は当時の国際法に乗っ取った軍事基地への限定攻撃でした。宣戦布告の遅れがみそをつけましたが、東京裁判では、宣戦布告文書の遅達自体を戦争法違反とは認定しませんでした。硫黄島は太平洋戦線で米軍被害が日本軍被害を上回った唯一の戦場です。米軍にとり本来は失敗作戦であったとも言える戦闘が海兵隊の勇猛さのシンボルに仕立てられてきました。何故、硫黄島が必要だったのか敢えて問う米国人は少ないでしょうが、日本都市爆撃の中継基地を確保するためだったのです。硫黄島での日本軍の抵抗が完全に収まっていない昭和20年3月10日には東京大空襲が敢行され、10万人が犠牲となりました。爆撃後帰路についたB29は硫黄島の滑走路上でゆっくりと翼を休めました。海兵隊の聖地は無差別都市攻撃と密接に絡んだ土地でもあったのです。原爆については、終戦を早めた、結果的により多くの人命を救った必要悪であったとの弁明が米国でなされてきています。原爆投下に係わる米国の意図については、このほかにも様々な背景要因が指摘されていますが、いずれにせよ原爆投下は文民に対する無差別攻撃で、当時も今も人倫に反し、国際法違反である可能性が高い行為です。
この歴史認識問題に我々としてできる何らかの対処策はあるのでしょうか。日韓では共同歴史研究が実施されています。基本的論点で両者の歩み寄りは難しく、立場の違いを合意する程度ですが、今後も継続されることになるでしょう。日中でも同様の作業の実施が叫ばれています。これらの作業には、第三国の研究者の参加が有効であると言われており、私もそう思います。日米の間も本当は、歴史認識のすりあわせが必要だと思います。今後、新たに発見される事実があるとすれば、それは日本の立場を補強するものも含まれると思われます。実際日本は出すものは出し尽くしたので、これから立場を悪くする新事実が出てくることは余りないのかも知れません。「新事実の発見」でなくとも、米国民に余り知られていない歴史的事実を彼らに知らしめることだけでも有効であると思います。この「事実の再発見」を米国人に促すような活動を工夫し実施することができれば、それは日米歴史認識のギャップの縮小に貢献するかも知れません。
では日米同盟の相手先の米国の立場を考慮しなくてもよいのか。日米を取り巻く現実を無視することが良策なのか。私は、そうは思いません。日本の国益の最重要の部分が米国との共存共栄に係っている今日、本件で日本は大人の対応を求められています。歴史認識是正を追求するあまり対米関係を悪化させるのは愚策です。歴史よりも現在、未来の方が重要です。現実問題として、聞く耳を持たない人に、本件のような「どうでもよい込み入ったこと」を縷々説明しても逆効果に終わる公算が大です。では米国に暮らす日本人はどうすべきなのか。
まず、状況をわきまえた毅然とした態度が大切でしょう。米、中に宥和すればうまく行くものでもありません。短期的に一波やり過ごすことができても、中長期的に信頼、名誉、誇りといった大事な財産を毀損しかねません。問題が持ち上がった時、冷静でバランス感に優れた反応が必要です。もっと日本の言い分や日本人の声が米メディアに反映されることも重要です。今後も歴史問題はずっと続くでしょう。20世紀前半における日本の歩みの公正な評価が定まるのはこれからです。その日のために我々は日本からの歴史認識視点をバランス良く、科学的根拠(新事実の発見)を添えて、内外に提示し、忍耐強く積み上げて行かなければならないのです。但し、あくまで冷静に、事の軽重を見失わないように注意しながら。
自分の経験からの帰納的感想ですが、高校レベルでの近現代史をもっと真剣に教えるべきではないでしょうか。私の出身校の場合は、近現代史は、受験にあまり出ないからといって授業で殆ど取り扱われなかったように思います。逆に近現代史を受験体制にもっと組み込んだら良いと思います。日本史は1500年もあって、なかなか全部を扱うのが大変ですが、古代から同じウェイトでやる必要はないでしょう。日本人全般が肝心の現代史に疎いのでは、国益に悖ります。教えにくいからと言って回避せず、両論併記でも何でもよいから、これからの若い世代の日本人自身が歴史問題につき、自分で考え、良い判断を下すことができるように、国家として、中・高校レベルの近現代史教育の充実に取り組むべきであると思います。
Ⅱ.日本人のアイデンティティー(地域社会との付き合い)
後半のアイデンティティーの問題については、テキサスに纏わる話題を織り込みながらできるだけ簡潔にお話致したいと思います。日系人の話をした後で我々日本人コミュニティーのことを取り上げたいと思います。
テキサスへの日本人移住者の走りが西原清東です。当時彼は政友会代議士であり、また同志社大学学長でもありました。1904年に米作指導のためヒューストン近郊のウェブスターに移住し、仲間とともに日本人ライス・コロニーを築きました。西原達が開拓したこの地には現在NASAのジョンソン・スペースセンターが建っています。日系人ではありませんが、テキサスに縁のある日本人に志賀重昂がいます。1899年にサンアントニオのアラモ砦を訪れ、国のために玉砕した守備隊の話が戦国時代の長篠の戦いでの鳥居強右衛門の故事によく似ているとして、漢詩を詠んでその愛国的行動を称えました。帰国後その漢詩を石碑に刻んでアラモ砦に寄贈し、いまでも砦内の一角にその石碑が残っています。志賀は地理学者でありましたが、サンアントニオからエルパソに向かう途中、アルパインを訪問し、地元の師範学校で同地に天文台を設置することを提唱しました。地形的にその辺りが北米大陸の最高地で、気象条件にも恵まれているのがその理由です。彼の提言は、付近のデービス山頂にマクドナルド天文台が設置されることにより後日実現しました。栗林忠道中将は硫黄島の最高司令官として、当時米国で最も畏怖された日本人だと言われています。同中将は、カナダ、アメリカでの駐在経験がありエルパソのフォート・ブリスにも滞在していました。
テキサスと日系人を繋ぐ最大の縁が「1944年北仏ブリュエールでの日系442連隊によるテキサス歩兵141大隊(ロスト・バタリオン)の救出」でしょう。この4月ヒューストンのホロコースト博物館で、日系人部隊によるダッハウ収容所解放と杉原千畝在リトアニア領事による通過ビザ発給に関する2つの展示会が開催されました。そのオープニングの際に442部隊関係者も参加した日系人集会がヒューストンで開催され、その模様やベテランへのインタビューがテレビでも放映されました。
集会では、戦時中のインターンメントを始めとする日系人の苦難の歴史について語られると共に、2世部隊である442部隊の活躍や戦後のリドレス運動についての報告がなされました。日系2世部隊の苦難と活躍は、日系人ならずとも胸を打つ逸話ですので、少し長くなりますが、状況説明をしてみたいと思います。ハワイでは米本土と異なり、いわゆるインターンメント・キャンプは設けられませんでした。ハワイ出身日系人は100歩兵大隊を編成し、欧州戦線で大活躍をしました。米本土の日系人は2世であっても敵性外国人として両親とともにインターンメント・キャンプに収容され、米国軍に入隊できませんでした。忠誠登録を実施しやっと入隊志願が許された米本土日系二世とハワイ日系二世からなる混成442連隊が編成され、欧州戦線等に投入されました。442連隊は100歩兵大隊と並び、最も武勲を挙げ勲章を得た部隊として名を馳せることになります。やがて100大隊は損耗が激しくなり、442連隊に吸収されます。442連隊には、522砲兵大隊(アイゼンハワーが選抜した最優秀砲兵部隊)が付属していましたが、これが本体と切り離されてドイツ戦線に投入されダッハウを解放したのです。
「北フランスのブリュエールに包囲されたテキサス141大隊救出のため他部隊が2度出動したが、失敗。442連隊が投入されました。テキサス141大隊211名(64人戦死)を救うため、442連隊は、5日間で1300人中800人が死傷(300人が戦死)しました。2世部隊は、自分たちが消耗品として扱われていることを百も承知で、この挑戦に挑みました。インターンメント・キャンプで待つ親兄弟のためにも名誉奪回の機会と捉えたのです。」以上は、今週サンフランシスコで開催された日系人と全米公館長の会議の席上、442連隊出身のダニエル・イノウエ上院議員がその基調講演の中で使われた叙述をそのまま借用したものです。戦後、442連隊ベテランは当時のジョン・コナリー知事からテキサス名誉市民として顕彰されています。
サンフランシスコの日系人と在米公館長の会議は今回で3回目ですが、会議や社交の席で、普段なかなか聞けない日系人の代表の人たちの胸の内を聞くことができ、とても参考になりました。正直なところ、これまで日系人と在米公館との間で活発な交流があるとは言えない状況でした。これは、日系人社会と日本との関係が今日まで疎遠であったことと無関係ではありません。何故、そうであったのか。戦後の日系2世は、自分たちの苦い経験と差別偏見への反応として、日本人らしさを殺して米国民に成り切ろうとしたのです。自分たちの子供には日本語を教えず、日本の文化にも関心を寄せませんでした。他人種との通婚が盛んに行われ、混血が進みました。しかしながら近年は、嘗ての貿易戦争も終わり米国の同盟国であり且つ先進文明国としての日本のイメージが徐々に改善したこともあり、日系人の三世、四世の間に日本への関心の高まりが見られます。漫画等に代表される日本のポップ文化の新たなブームと共に自分のルーツへの回帰現象が見られるのです。混血により血が薄まり日本人アイテンティティーとどう向き合うのかという切実な問題とも無関係ではないでしょう。
今はしっかりと米国中産階級に根をはやした日系人ですが、未だに差別の問題があるようです。リドレス運動の結果として、法律的な決着は見たとはいえ、歪められた日本人のイメージが米国社会に残っていますし、外見がアジア系なので、米国人であるにも拘わらず、日系人としてのカテゴリーでしか認知してくれないという不満もあると聞きました。アジア系移民の先駆者としてアジア系をリードし経済的にも成功を収めてきましたが、周りに仲間がおらず、加えて非白人に対する微妙な人種差別を感じると言います。
ところで、日系は、アジア系移民の先駆者だと申し上げましたが、当時は最初で最大の集団であったものが、その後の中国、台湾、インド、ベトナム、韓国からの移民の増加により、主要なアジア系米国人の中ではむしろ少数集団になってしまいました。米国社会において独特の存在感を持つ日系人集団も、時代が変わって今は社会的弱者化の懸念に苛まれるようになってきたのです。
民主主義の下では、数の論理が重要です。質と言いますか富でも影響力を買えますが、建前の世界では量すなわち投票数がものを言います。政治家が有権者に媚びるのは古今東西を問いません。多くの投票数を持つ越、中、印等のアジア系社会は権力者である政治家の関心を引き優遇されるのです。数の上で少数の日系は見過ごされることになります。おまけにもしも日系人がおとなしく、消極的で、政治的無関心であるとしたら、彼らには多くの選択肢はありません。すなわち混血により血を薄めるかアジアの多数派に寄り添うかの二つです。
アジアの多数派に身を寄せると言っても、これがなかなかやっかいです。任地であるヒューストンの日系人社会についての個人的観察から申し上げれば、アジア系の集まりから距離を置く日系人が多いように感じられます。地域活動への参加にあまり積極的ではない人が多いためかも知れませんが。但し、地域社会で成功している日系人ほどアジア系と広く接点を持っているのも事実です。日系人の存在を示すには、アジア系経由でないとまともに示せないのが今日ヒューストンの日系人の置かれた状況です。アジア系内での尊敬を獲得する事が大切です。日系人及びその出身国日本は、文化、先進国、富、穏和、長老としての人望等多岐に亘る魅力というかレガシーを持っています。これらは他の新興アジア系集団には魅力として映るべき財産です。彼らとのつき合いは、短期的には持ち出しでしかないかも知れませんが、中長期の入会権確保のためと思えば、必要且つ賢明な投資であることは間違いありません。
アジア人というアイデンティティーは、当のアジアでは実体がありませんが、米ではアジア系米国人というアイテンティティーが市民権を持ち始めつつあります。先ずは、アジア系で結託して政治力をつけ、白人主流派と対等の発言力を確保する。アジア系移民にとって、エンパワーメント活動を行う上でのキー・ワードとなっています。アジア系米国人の主流は数の上でも現在は中国系でしょうが、日系もレガシーを使って食い込みたいところです。
さて、いったいお前は何を言いたいのだとフラストを感じている方もいらっしゃると思います。ようやく、日本人社会の話に辿り着きました。私が申し上げたいのは、日系人社会の状況は、実は、米国における我々日本人社会そのものではないかということなのです。日系人社会が抱える課題の多くはそっくりそのまま日本人社会の課題なのではないか。台頭する他のアジア系集団、ヒスパニック系集団の前に、テキサスの日本人社会が、このままではどんどんマージナライズされて行くのではないか。もっと真剣に対応を考え、それを実践して行く必要があるのではないかということです。
日本が一番という日本人のメンタリティーについては私もそう感じる一人でよく分かります。いずれ近い将来日本に帰るのだから、米国ではお客様として、できるだけ苦労せずに楽しく過ごしたい。このような考え方は良く理解できますし、誰も文句を言う筋合いのものでもありませんが、日本人社会全体となるとどうも勝手がよろしくないように思うのです。大部分の日本人は日本の方が米国よりも良い所だと思っていますが、このように感じる米国在住者は例外なのです。殆どは、自分及び自分の家族の未来は米国にあると信じ、石にかじりついても米国に留まりたいと思っている人達です。我々日本人のテキサスでの生活や商権を守るために、好むと好まざるに拘らず彼らと競争する局面にも遭遇いたします。人口増加に加え、命懸けで米国社会への定着努力を行っているアジア系集団に伍して行くには、日本の看板を背負っているとはいえ、我々にもそれなりの覚悟と努力が必要だと思います。
それでは、具体的に何をしたらよいのか。それは、地元地域社会にもっと一丸となって日本のプレゼンスを示せということですし、また、もっと地元諸団体との付き合いを良くせよということです。各地の日本関係団体の活動を盛んにすることはその第一歩でしょう。特に、日本関係諸団体が結束して共同事業を実施し、地域社会に存在感を示すことができれば素晴らしいと思います。地元との付き合いが大切だということに誰も異論はないでしょう。会社単位で、また、個人的にも大いに地元と交わり、地域社会への奉仕活動等を実践なさっている方も多数いらっしゃると思いますが、それでも全体として見れば少ない。平たく申し上げれば、例えば、もっと積極的に地元の社交行事や各種ビジネス会合等に参加なさっては如何でしょうかと言うことなのです。皆様方がお忙しければ、若手職員でも良いでしょうし、米国人スタッフでも構いません。日本人ビジネスマンの影が薄くなると、日本が過小評価され、必要な情報も入って来なくなってしまいます。たかがパーティーの話ですが、これが積み重なり、日本人社会全体の地盤沈下に繋がりかねないのです。米国はボランティア社会です。ボランティア活動は顔を売り、人と出会う場です。米国人はそこで友人やビジネスを見つけていると聞きます。課税控除制度に後押しされた面もあると思いますが募金活動も盛んです。募金への参加は、良き企業、良き市民のノブリス・オブリジェと考えられ、また、効果的な宣伝にもなるようです。
更に、穿った見方をすれば、地元社会との深い付き合いが、これからの日本を背負って立つ人材の育成に役立つかも知れません。ビジネスの世界でも、今盛んにルール作りに主導的に関与すべしとか世界標準を獲得せよということが言われております。この分野が将来の日本経済の命運を担う言うわけです。オリンピックで日本人選手が金メダルを取ると次の大会ではルールが変えられてしまうとか、2世代携帯電話で世界標準が取れなかったとか、どうも、この方面での日本の成績は芳しくありません。技術は負けていないのですが、話術ともっともらしい理屈で利害関係者の意見を纏めて行く能力には長けていないのです。政治力がないと言っても良いかも知れません。他方この能力が日本の未来を決するほど重要だとしたら無策を決め込む訳には参りません。私は、例えば日本企業の若手社員が地元の青年商工会議所の活動に参加され、大変な苦労をしながらも異文化摩擦の下での対処の仕方を学ばれることが一つの答えなのではないかと思います。
以上、長々と申し述べて参りましたが、要するに、テキサスの日本人ビジネスマンの皆様、一致団結してもっと日本の存在感を示そうではありませんか。