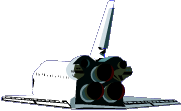在ヒューストン日本国総領事 加茂佳彦

本日は年の瀬のお忙しい時分に、谷口先生を囲む会に皆様多数ご参加頂きまして、ありがとうございます。谷口先生には、大変お忙しい御日程の中で今夕時間を作って頂き感謝申し上げます。谷口先生は今回、現在手掛けられて居られる・ヒューストンアジア協会委託のプロジェクト(アジアハウス)の設計模型の発表を行うため当地を訪問されていると承知しています。本会は同時に恒例のJBAと総領事館共催の懇親会をも兼ねております。谷口先生のお話を伺ったり、記念写真を撮ったり、東京ガーデンのすしをほおばったりと皆様に愉快に過ごして頂ければ幸いです。
日本の建築家が何故世界でも高い評価を受けるのか、日本文化の伝統となにがしかの関係があるのか。後刻、谷口先生からご意見をお伺いしたいと思いますが、私なら「確かに、関係がある。日本人建築家は、日本の美や工芸の伝統により育まれたデザイン感覚を受け継いでいる。日本文化の精髄の一つが建築デザインだ」と申し上げることになるでしょう。これに対して、ダラスの大富豪で、嘗て大統領候補であったロス・ペロー・シニアは多分こう言うでしょう。「何時の世も、ブレークスルーを達成し、世の中を動かすのは一握りの天才だ。彼らの創造性、発想が人類を前進させる」と。
日本文化紹介を生業としている私が、日本文化のレパートリーの一つとして建築を持ち出すのに対して、ペロー氏は、建築家個人の創造性に重きを置きます。なるほど、この視点はとても大切だと思います。谷口先生の創造性が日本の土壌とまったく無縁だとは言えないでしょうが、先生は、日本文化だけの具現者ではない。様々な要素を消化、吸収し、磨いた感性が、先生の作品に命であり、その建築デザインには、「メード・イン・ジャパン」のロゴは不要でしょう。むしろ、特定の文化や国境に囚われない普遍性にこそ目が向けられるべきだと思います。
さて、概して、日本人社会は米国で「アジア」と名の付く団体と疎遠です。確かに、実際のアジアや日本では、「アジア人」という観念に実体はありませんし、「アジア」への帰属意識もありません。過去には「日本」だけで勝負出来るという自負も実績もあったかも知れません。でも今の米国では「アジア」の括りは無視出来ません。かつては「アジア」=「日本」で通っていましたが、今は「エイジャン・アメリカン」という概念が破竹の勢いで根付いています。「アジア」という拡大するフィールドでどう陣取りをするか、我々には戦略的思考が求められていると思います。
今回、谷口先生がアジア・ハウスをデザインされるのは、日本人社会にとっても大いなる僥倖です。これを契機に、米国の未来を映す都市と言われるヒューストンで、アジア社会との付き合いをもっと深めて、米国における日本人社会の先鞭をつけたいものだと思う次第であります。その意味でもアジア・ハウス建設実現のために日本人社会としても応分の貢献を行って行くことが適当ではないかと考えます。皆様方のご賛同が得られれば幸いでございます。
ご静聴ありがとうございました。